2011/05/31
2011/05/30
電力ロガーをつくろう(準備編2)
主要パーツが届く前に、持っているパーツで事前仮組み。XBeeシールドの蛇の目部分狭いってw。10×11だもん。いや、青い端子パーツがデカすぎるだけかな。のこりのパーツははDIPのブリッジダイオードとコンデンサと配線になります。基本的にgalileo7さんとこのWattmeter2の実効値の回路。Wattmeter2の基板と比べてXBeeシールドだと蛇の目の面積の関係で2系統(無理して3系統)までしか載せられませんが、その代わりにトータル価格が安いです。本当はサンハヤトのArduinoシールド基板にXBee変換基板を載せるのが一番安くて一番広いんかな。
そして、お試ししてたArduino電力測定。本日帰宅したら電気切れていました。microSDのログ見る限り44時間くらいかな。XBeeとLCD付きの回路をくんで1日持つ程度かな。ちゃんと回路も絞って、プログラムも最適化して測定の合間はSleepさせるようにすればもっと持つでしょう。
あと、ひとつ準備したの忘れてた。
クランプ計測用に1mのテーブルタップを買ってきて、ケーブルの途中をカッターで引き裂きました。いまどきのタップってケーブルの被覆に境目が無いのが多くて困った。これはすこしばかり溝があったので購入。壁のコンセントから給電できる機器は、すでに持っている計測技術研究所のOEMのサンワサプライの「ワットチェッカー」での測定と比較するのだ。ワットチェッカーはちゃんと電圧も取得してるから、より正確なはずだ。
いままでとは違う気象・気候
子供の頃は夏の暑さも32度を超えるくらいが数日だったのだが、今じゃ8月なんて毎日真夏日みたいな感じで・・・。5月~12月まで台風がくるやら。日本の四季はまだあるけども、住みやすい環境ではないですね。特に首都圏。生まれ故郷のほうがやはり過ごしやすい。この東京よりも若干緯度は低いし経度も西ですからね。
2011/05/29
電力ロガーをつくろう(準備編)
なんか、冷房も暖房も入れない時期なのに電気代が思ったより高かった。原因追及の為に電力ロガーを作成します。うちの分電盤はこんなので、
単相3線式。おかげ様でリビングのエアコンは200V機を使っている。
電力を調べるには超小型クランプ式交流電流センサCTL-10-CLSで赤い線と黒い線の挟んでそれぞれの電圧を測定して足し合わせれば良いんでないかな。電圧は測定せず100Vと仮定して。
しかし、この分電盤の近辺にはACコンセントが無い。分電盤から取れるじゃんと言われてもちと怖いので、ArduinoはエネループのKBC-L2で駆動します。計測値はXBeeでPCへ飛ばす予定。まぁこの電力ロガーネタは先人がたくさんいらっしゃるので参考サイトを見ながら頑張ろう。くれぐれも感電しないようにだな。
2011/05/28
ストロベリーリナックスI2C液晶をbreakout化
I2Cバスのプルアップ抵抗をいちいち付けるのが面倒なのとヘッダピンが細いので間に基板をかまして対策しました。(ホントはI2Cバスにつなぐ他のスレイブとで抵抗値は調整が必要でしょうけど。あくまでプロトタイピングであって量産じゃあないので固定で良いかと。) breakout化って程のことでは無いですね。
 抵抗の足を使って半田付けします。新ピンヘッダを指すべきホールが一度半田で半分埋まってしまって吸い取り線を使いました(汗。
抵抗の足を使って半田付けします。新ピンヘッダを指すべきホールが一度半田で半分埋まってしまって吸い取り線を使いました(汗。
 I2C基板と変換基板の間が狭いです。1/4Wの100本入り100円抵抗なので・・・。表面実装のチップを使って綺麗に出来ると良いです。
I2C基板と変換基板の間が狭いです。1/4Wの100本入り100円抵抗なので・・・。表面実装のチップを使って綺麗に出来ると良いです。
ちゃんと動作も確認。もともと携帯電話の液晶パーツだったんですかね?一番上にそれっぽいアイコン部分があります。2行表示というとDoCoMoだと20x系の頃とか。
2011/05/27
2011/05/25
2011/05/24
2011/05/22
秋月版Arduino出動
作成した秋月版ArduinoをベランダセンサーのUNOと置き換えるべく作業。
 キットなので、表面実装のパーツは無く、裏面にもバリバリと半田付けしたパーツの足が出ております。一応、ニッパで短くはしたのだが。ここに粘着テープ付きの面ファスナー(マジックテープ)を付けても強度が落ちそうで。工夫が必要だ。
キットなので、表面実装のパーツは無く、裏面にもバリバリと半田付けしたパーツの足が出ております。一応、ニッパで短くはしたのだが。ここに粘着テープ付きの面ファスナー(マジックテープ)を付けても強度が落ちそうで。工夫が必要だ。
 んで、子亀のシールドの方のsparkfunのProtoShieldが入っていたプラケース。こいつの一部が使えそうなので、利用することにした。秋月基板の3箇所の穴と位置を合わせて、ハンダゴテで穴あけ。昔懐かしい臭いがした。
んで、子亀のシールドの方のsparkfunのProtoShieldが入っていたプラケース。こいつの一部が使えそうなので、利用することにした。秋月基板の3箇所の穴と位置を合わせて、ハンダゴテで穴あけ。昔懐かしい臭いがした。
 外のペットボトル製センサーケースからブレッドボードごとUNOとセンサーをひっペがしてきて載せ替え。最初湿度センサーの配線を間違えていて、マイナスの湿度が出てましたがw。修正しました。
外のペットボトル製センサーケースからブレッドボードごとUNOとセンサーをひっペがしてきて載せ替え。最初湿度センサーの配線を間違えていて、マイナスの湿度が出てましたがw。修正しました。
 外に設置。この時初めてマイク製風センサーと接続したわけですが・・・。値が帰ってこない。CPUが変わってメモリが半分になったので、サンプリングのfloatの配列が取れないと推測。数を半分に減らしたスケッチを送り込んで無事動作を確認。
外に設置。この時初めてマイク製風センサーと接続したわけですが・・・。値が帰ってこない。CPUが変わってメモリが半分になったので、サンプリングのfloatの配列が取れないと推測。数を半分に減らしたスケッチを送り込んで無事動作を確認。
また、秋月基板はUSB端子のでる方向が本家系とは90度違うのでUSBケーブルの取り回しに時間がかかりました。
最初に部屋の中から引いてくる時に2本ともUSB延長ケーブルにしておけばよかった。
以上で、乗り換え完了です。
2011/05/21
秋月キット版Arduino完成

キットに10KΩの抵抗が入ってなかったりしたが、無事に完成。
ブートローダはここHPの手順で行けました。Windows7 64ビットでも何ら問題なし、というかあっさり行きすぎてびっくり。FTDIのドライバは手順HPのバージョンではなく最新版で。最初水槽ポンプと繋がっている方のFTDIチップのCOMポートを掴んでしまってたけど、ハブから抜いて事なきを得た。昨日の夜ちょっと遊んでいたLM35のシールドを子亀載せして、スケッチも転送して無事に動作が確認できました。
Arduino UNOと比較してみると若干横幅が長いです。ただしUSBポートがminiBなので扱い易いです。あ、AVRマイコンチップはATMEGA168P-20PUなのでUNOの328Pと比較するとFLASH、EEPROM、SRAMが半分なだけです。わしの書いてるようなセンサー凝っていないプログラムならどっちでも問題無いね。
ケーズデンキ、ケイヨーデイツー、ヤサカ
地図サイトをを見ていたら大きめなケーズデンキがあったので本日午前中に行ってみた。郊外型の1Fが駐車場で2Fが店舗のタイプ。立川ビックカメラの様にフロア間の移動が不要なので楽だ。お値段はどっちが安いのだろうか?USBハブとLEDハンディライトと電線を購入。
芋窪街道を北上して泉体育館の横を通っていなげや本店の交差点を右折。五日市街道の1つ南の通りを東進。ケーヨーデイツーを偵察。1フロアだが良く行く青柳のデイツーとは微妙に品揃えが違う。何も買わずに戻って東へ。
でんきのセキドは特に寄らず、ヤサカに寄った。おー、いろいろあるなぁ。ジフィーセブンも売ってるし。店舗北側の園芸コーナーが充実している。キャンプ用ダンボールスモーカーが1480円だったが我慢した。ここではフェライト磁石と熱収縮チューブを購入。
そのあと立川通りから弁天通経由で国立駅前まで行って、たましん歴史資料館で多摩のあゆみ142号最新刊をゲットして北プラザの図書館で3冊借りて帰宅。普段、立川北部へは来ないけど、たまに散歩するのはやっぱ良いな。
2011/05/20
秋月いろいろ発注
昨日のエントリーでも書きましたが、足りないパーツと新しいパーツを発注。するってえと新しいパーツを使うために足りないパーツが出てきて再発注ってコンボになるのだな。今回Arduino互換キットを新規にぽちっておきました。自分で半田付けしないと行けないけどお安いです。プロトシールドを付けて、ベランダのペットボトル百葉箱の中身と入れ替える予定。プログラム的にはATmega328PでなくATmega168でも余裕サイズだしね。
そして「ちょっと測定」としてLM35の温度計。黒いトランジスタみたいなのが温度計センサー&IC入りのチップです。測定値は結構いい感じでした。ファーストArduinoなんかにはLEDも良いけどこういうセンサー系も良いのではなかろうか?
2011/05/19
親亀子亀孫亀
Arduinoのボードたち。コネクタで上手く積み重なります。一番左のが本体のArduino UNO。
これはプロトシールドに小さいブレッドボードを載せた物。ブレッドボードの下には蛇の目基板があって好きな回路を作成できるように成っている。その上にブレッドボードを貼りつけてさらに半田付け無しで遊べるようにしてみた。
これはmicroSDシールド。左1/3がキモで、右側の蛇の目基板部分は上のプロトシールドと同じく、お好きに使ってネの広場。microSDですが使えるのは2Gまでであります。蛇の目部分に秋月で買ったRTCモジュールとキャパシタを載せて、ログ記録用シールドとしますかね。ログに必須の時刻記録ですけど、Arduino自体には時計機能が無いのでRTCで補完。RTC自体もバックアップ機能はないのでキャパシタで補完。キャパシタの在庫がないので発注しました。1F5.5Vのやつを縦型横型で1個づつ。昨日の記事のの歯車センサー用にMAX662も。
2011/05/18
秋月でパーツを通販
言わずと知れた秋月電子通商で通販でパーツを買いました。圧電サウンダー4個で100円。フルカラーLED 100円。RTC-8564NB 500円。MPL115A2使用大気圧センサーモジュール 700円。

一番怪しいのがこのOH182/E。非接触回転速度センサー。歯車の歯のでこぼこを磁界で検出し出力しますっていう磁石付きセンサー部とIC部がつながったような格好のパーツ。2個セットで300円。映画のフィルム状のは包装です。垂直ペットボトル風車の軸にギア付けて回転数で風速でも測定しようかとか。ただ添付の資料のサンプル回路だと12V使っている。5Vでも動きそうではあるがDC-DCコンバータで5V→12Vしたほうが無難か?あ、このチップ別名KMI15/4というらしい。

あとこの基板。本来は表面実装のパーツを付けるみたいだけど、適当にはんだブリッジさせて雨降りセンサー(≠雨量センサー)につかえないかなとか。雨粒が流れるように傾斜させて置きます。とりあえず、ひと通り欲しそうなものは買い込みました。
2011/05/17
2011/05/15
2011/05/13
webcam微調整・・・してみたが
昨夜いじったwebcam設定まわり。今まではwebcamの設定のdelayを指定して、カメラとubuntu PCは常につながった状態でインターバル撮影していたから気づかなかった。今回シングル撮影にしたら、昼間は真っ白け!カメラが光量を把握するまで時間がかかるようだ。試しにwaitを200で指定してみた。結果は明日の昼間にわかるが、明日は土曜当番で出勤なので再調整できません![]() 。
。
とはいうものの、夜だけど撮影のタイミングにカメラを見張ってみた。waitの時間が終わるまでタリーランプがつかない。タリーも一瞬だけだ。ってことはwaitを足しても意味なさそう。LogicoolのRightLightテクノロジーとかのWebCameraじゃないとだめかなぁ。って事で一旦元に戻します。webcamを連続モードに戻しつつ画像はローカル保存にして、そのローカルのファイルをCronで自借鯖とPicasaに上げるようにすれば良いのではないかな。
2011/05/12
雨なのでビックカメラに寄る
雨予報なので公共交通機関出勤。でも、朝は雨が降っていなかったので、職場最寄りの駅からは職場バスには乗らずに25分ほど歩いて出社。
帰りは立川でビックカメラ&ユザワヤへ寄った。フロアの配置換えをしたようで探すのに時間と手間がかかる。こういう事もあってネットショップのほうが好きだ。ぶらぶらショッピングなら違うのだろうけども。購入物は、エポキシパテ(水中用)、光硬化パテ、自己融着ブチルテープ、電線替わりのLANケーブル。二股になるUSBハブ(こんなかんじの奴)は売ってなかった。四つ股はあったが。ユザワヤにドーム型のプラスチックのケースがあった。アサガオカメラ設置時に水まきの水をかぶらないようにケースに使えるかな。
そして帰宅後、webcamの設定を変更。webcamコマンドによるインターバルじゃなく、cronでの時刻指定起動に変更。ついでにgoogleCLにてpicasaにもアップするようにしてみた。あとはcronで月一の月初にアルバムを作成するようにすればOKかね。picasaのアルバムは1,000枚/アルバムの制限があるのです。1時間に1回を24時間31日だと744なのです。
そういえばpachube。いつのまにやら福島の原発近辺に大量のガイガーカウンターのfeedが出来ている。運用よろしく頼みます<feederの作成者
2011/05/11
2011/05/08
2011/05/07
西洋おだまきと芽が出ないアサガオ
西洋おだまき。マンションの空き缶捨て場の横に咲いています。
そして、二週間前に蒔いたアサガオ。まだ芽が出ません。本日はプランターに土を準備して、ヘブンリーブルーも6つほど蒔いてみた。6つなのはジフィーセブンの在庫が6個しかなかったからです。買いに行かないと。
2011/05/06
雑多なこと2011/05/06
・ubuntu 11.04のunity。リモートデスクトップで画面書きなおしが帰ってこないし。超使いにくいのでclassicのno effectにした。メインで使うマシンじゃないし。Arduinoのイーサネットシールドのかわりなので。そういう用途でubuntu使うなって?だって他のディストリビューションよりドライバ周りが楽できるんだもん。
・趣味を兼ねて、実益とは兼ねることができないという気象予報士をうけてみようかなと。物理数学部分をどう克服するかが問題だ。
・本日「立夏」です。っても暦が旧暦とはずれてるからなんともね。でも職場は暑くて死にそうでした。
・昨晩最後に作った回路はこんなん↓。この絵はFritzingというソフトで描けます。便利ですね。で、今晩はsparkfunのシールドの半田付けしてました。
25章配線図



















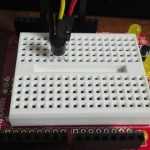
















 も使って、あしかがまで。フラワーパークと栗田美術館。天気良かった。
も使って、あしかがまで。フラワーパークと栗田美術館。天気良かった。
